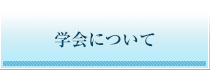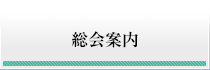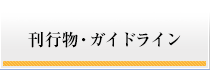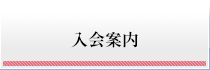理事長挨拶

日本気胸・嚢胞性肺疾患学会
理事長 伊豫田明
本学会は1977年に「気胸研究会」として発足し、1997年に「日本気胸学会」、2003年から「日本気胸・嚢胞性肺疾患学会」へと呼称を変更して現在に至っております。
本学会は、原発性(特発性)自然気胸、続発性自然気胸【肺気腫、間質性肺炎、肺癌、転移性肺腫瘍、胸腔子宮内膜症、Birt-Hogg-Dubé(BHD)症候群、リンパ脈管筋腫症(lymphangioleiomyomatosis)、肺Langerhans細胞組織球症、Ehlers-Danlos症候群、Marfan症候群などを基礎疾患とする】、外傷性気胸、新生児や小児における先天性肺気道形成異常(congenital pulmonary airway malformation:CPAM)などの先天性嚢胞性肺疾患など多彩な疾患を対象としています。
気胸・嚢胞性肺疾患については、多様な病態から様々な視点による診療・研究が重要となります。したがいまして本学会の活動としてに内科・外科・小児科・放射線科・病理診断科の医師が一堂に会して討議する学術集会や学術論文による誌上討論の場として日本気胸・嚢胞性肺疾患学会雑誌が重要であると考えています。
気胸・嚢胞性肺疾患については未解明な部分が多く、気胸の病態解明や治癒率の改善に向けた対策が課題であり、学術委員会を中心としたプロジェクトとして「肺病態から見た気胸」を学会誌増刊号として2020年に発刊を行い、課題に対して多施設共同研究を進めています。
気胸や嚢胞性肺疾患は、呼吸器外科医、呼吸器内科医など呼吸器系専門医のみならず、呼吸器を専門としない内科、外科、総合診療科、救急科など多くの診療科がかかわる疾患であり、本学会としては、多くの医療従事者さらには広く一般の方々にも、気胸に対する認識を高めていただくことが気胸・嚢胞性肺疾患の治療成績向上に極めて重要と考えております。本学会の活動につきまして皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。